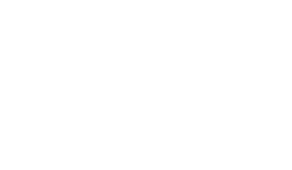目次
効率的に物理サーバを設置できるラックマウントサーバ
物理サーバには名前のとおり物理的な筐体があり、その中にCPUやメモリ、ストレージ、電源などさまざまなデバイスが組み込まれています。こうした物理サーバのハードウェアについて詳しく見ていきましょう。
まず、物理サーバの筐体はいくつかの種類があります。一般的に使われているのはラックマウントサーバなどと呼ばれるもので、専用の棚(サーバラック)に取り付けて使います。ラックの幅は米国電子工業会(EIA:Electronic Industiries Alliance)で19インチに標準化されており、市販のラックマウントサーバは基本的に19インチラックに収まるように設計されています。

ラックに取り付ける機器の高さも、やはり米国電子工業会によって規定されており、1.75インチを標準としています。この1.75インチの高さを「1U」と呼ぶことから、1Uサーバという用語もあります。また、2段分の高さを持つ「2Uサーバ」や、4段分の「4Uサーバ」といった大型のサーバも存在します。


富士通の1Uサーバである「RX1330 M1」「RX2530 M1」
このラックマウントサーバが一般的になった背景には、サーバルームやデータセンターのスペースを有効に活用したいというニーズがあります。サーバには、デスクトップパソコンのようなタワー型の筐体を持つ製品も存在していますが、基本的に積み重ねて利用することが想定されていないため、縦方向の空間を活かすことができません。一方、標準的なサーバラックは42Uの高さがあり、1Uサーバであれば42台も積むことが可能です(実際には、冷却などの問題から42台をフルに積むことはまれですが)。このようにラックマウントサーバはスペースを有効に活用することが可能なため、特に多くのサーバを利用する用途では広く普及しているのです。
クライアントPCと異なる物理サーバのハードウェア
サーバとクライアントPCを比較すると、内部に組み込まれているパーツにさまざまな違いがあります。分かりやすい例で言えばCPUでしょう。代表的なCPUメーカーであるインテルは、クライアントPC向けCPUを「Intel Core」シリーズ、サーバ用CPUを「Intel Xeon」として明確に製品ラインナップを切り分けています。
XeonがクライアントPC向けCPUと大きく異なるのはコア数です。1つのCPUの中で複数の処理を同時に行えるようにしたのがマルチコアCPUで、現在はIntel Coreシリーズにおいても4コアや8コアといった製品が存在しています。しかしIntel Xeonの上位モデルはさらにコア数が多く、ハイエンドモデルでは24ものコアを搭載する製品が登場しています。
メモリやストレージも異なります。サーバで使われるメモリは、メモリで発生したエラーを自動訂正する仕組みである「ECC(Error Checking and Correction:誤り検出訂正)」や、CPUとメモリ間でやり取りされる電気信号を安定化させる「Registeredチップ」を組み込んだメモリを使うことが一般的です。
大容量ストレージを実現するストレージアレイ
データを保存するためのストレージにもさまざまな違いがあります。たとえばHDDの接続において、クライアントPCではSATA(Serial Advanced Technology Attachment)が主流ですが、ハイエンドサーバーではSAS(Serial Attached SCSI)と呼ばれる方式でHDDを接続する製品もあります。SATAと比較した場合、SASは性能と信頼性に優れているほか、送信と受信を同時に行える全二重に対応するなどといった特長を持ち、特にストレージに対するI/O処理の負荷が高い用途に適しています。またストレージの信頼性や可用性を高めることを目的として、あらかじめRAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)構成が採られているサーバ製品もあります。
信頼性を高めるための工夫が盛り込まれていることも、クライアントPCと物理サーバの違いでしょう。たとえば物理サーバでは、複数のネットワークインターフェイス(NIC)を搭載し、一方のNICに障害が発生した場合でも別のNICで通信を継続できる冗長化の仕組みが組み込まれている製品があります。
仮想サーバを使う場合、これらの物理的なハードウェアの要素は仮想化ソフトウェアによって抽象化されているため、あまり意識することはありません。ただ、特に自社でIaaS環境を構築して利用するプライベートクラウドを運用する場合やベアメタルクラウドを利用するのであれば、こうしたハードウェアへの理解は必須であると言えます。